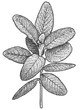top of page
従兄Kさんとランチ 話題は九鬼水軍宗家のこと 2019年6月27日
Kさんとランチ
従兄のKさんから電話が入る。「天皇即位と超古代史(文芸社文庫・2019)は読んだか?」というもの。その本はいわゆる「古史古伝(こしこでん)」から日本史を読み解くもので、九鬼水軍に関する記述があるのだが、その記述は京都の綾部(あやべ)九鬼家、兵庫の三田(さんだ)九鬼家に由来する史料に基づいている。
ちなみに、古史古伝とは「偽書(ぎしょ)」とも呼ばれ、古事記や日本書紀などの「正史」と対比されている。古史古伝は各土地の豪族がまとめたり、江戸時代には幕府の命によりその歴史を提出するよう命じられた際に、各藩は都合の良いように系図をまとめたものもあるという。良い機会なので、昼食を一緒にしながらさまざまに話すことにした。
九鬼家についてはその出自について議論がある。江戸幕府がまとめた「藩翰譜」(はんかんぷ)においては出自については、議論があり、ふたつの論が併記され今なお平行線を辿っている。ただ、九鬼嘉隆は信長・秀吉に仕えて数々の大きな功績をあげた経緯があり、綾部・三田の両家は、鳥羽・九鬼嘉隆の子孫であるため影響力は大きい。嘉隆は九鬼宗家から見ると第三分家にあたる。では、九鬼宗家に関する史料はどうなっているか?
Kさんは、もともとの九鬼水軍発祥の三重県尾鷲市九鬼町の九鬼宗家に関して、その本に何の記述もないのが不思議・疑問というもの。言外に不満の気配もある。それは、私も長くひっかかっていた。九鬼宗家に関する史料は残されてはいるものの、明治の高名な九鬼盛隆が系図上に残されているまでで、それも内容は限られているからだ。
Kさんは、従兄の中での最高齢。私よりも17歳上の88歳。長く財界で活躍した。高齢なのにその明晰な話し方は昔と変わらない。最大の特徴は人の話に丁寧に耳を傾けること。そして必要に応じて合理的な反論をし提案をする。それにはいつも脱帽してきた。その話し方は今回再会しても変わらず、ポイントは明確。つまり、九鬼宗家については偉人もいるのだから、もう少ししっかりまとめて発信しておいた方が良いのではないかということだった。ええ~、それを私にしろということか?どうもそうらしい。でも私も70歳。しかし私も本家ではなく分家筋の末裔なんですけど…。
さて、九鬼水軍といっても、知らない人が多いだろう。それについては別項で詳細を。
T君の急逝
5月23日の朝に、会社の先輩Gさんから一本の電話が入った。同僚T君が同日に亡くなったというもの。それには仰天し名前を何度も確認した。なにしろT君は、すぐ近所に住まいし、最寄り駅から良く一緒に歩いて帰宅するのはもちろん、数週間前まで一緒に食事をしたり、日常のメール交換をし、つい最近も電話で話していたのに… 生活習慣病と無縁で常用薬もなく、健脚で歩くことを億劫がらない人だったからだ。だからその事実をうまく呑み込めなかった。第一にまだ68歳なのだ。やがてお宅から葬儀日程のメールが到来しついに現実の事なのだと知った。
原因は、急性悪性リンパ腫(血液ガン)とのこと。5月5日の昼食後に、ひどい倦怠感に襲われ地域の拠点病院に救急搬送され、集中治療室で抗がん剤を投与したがガンの勢いに勝てず、23日に亡くなったそうだ。僅か18日間の入院。
あいにく葬儀に出席できなかったので、6月14日に、ご自宅を弔問する。ひどく雨が降っていた。穏やかな表情の遺影があった。伺ってさまざまなお話をしている間、令夫人は終始涙を流しておられ続けた。ああ、良いご夫婦だったのだなと思われた。
死は思いがけない所から訪れる。内蔵のガンや心筋梗塞、脳梗塞などは想定されるが、急性の血液ガンは想像し難い。自分にとっても思いがけない死の覚悟が必要な年齢となった。エンディングノートの作成が急務である。
2018年6月28日
本の断捨離をちょびちょび続けて来たが、捨てられない物は、スキャンしてPCに取り込む自炊作業も続けて来た。それらが、今、このウェブサイトの記事制作に活躍している。
特に便利なのが辞書・事典類だ。
中型・大型のものは、狭い机の上に複数広げるのが難しく、またその重さもあって出し入れが億劫になって来ていた。
それで広辞苑をはじめ字通、類語辞典、英和辞典などデジタル化されて販売されているものは可能な限り購入したり、インターネット利用もして来た。
しかし長く愛用し信頼して来た国語辞書や、歴史系などの事典、年表の類は、必ずしも、デジタル化がされていない。
例えば、講談社の「日本語大辞典」はもう30年近く利用し、改訂されるごとに購入して来た愛用品だ。デジタル出版はされていないのかを出版社に問い合わせたら、そのプロジェクトは既に解散してデジタル化の予定もないとのこと。
仕方がないので、現物をKinko'sに持ち込んでほぐして貰い自宅でスキャンした。ページ数は2500を超えた。岩波書店の「近代日本総合年表」も同様で800ページあまり。自分のサイトの記事作成にあたって、「日本水軍史」などもデジタル保存して来た。
デジタル化のメリットは、なんといっても、キーワードを打ち込むと縦横に検索されて、自分が知りたかった記事はもちろんのこと、それに関連する項目が多岐にわたって登場することだ。これは思いがけない発見につながり威力を発揮する。
もうひとつは、縦書き本が見やすくなったことだ。縦型ディスプレイをPCの第二画面としてつないだら、和書がスクロールいらずで読めて、とても便利になった。拡大も自由自在。なんでこれまでPCは横型利用ばかりしていたのだろう。
第二画面を利用しながら第一画面では別作業もできるので、作業にストレスがない。
なぜ、古い辞書を使い続けるのか?
それは、個人知と集合知の違いにつきる。紙の辞書・事典は、項目ごとに記事作成者名が入っている事が多く個人の責任が明確だ。
また書物は、字数が限られているので、内容が凝縮されてポイントが明解である。そして、出版された当時の、紙の雰囲気や、きれいなフォント、写真などがそのままに伝わって来る。
一方で、Wikipediaは集合知である。便利ではあるが、誰が書いたかがわからない。情報は長く冗長になりがちで、必ずしも核心をついていないので、自分の知りたいことになかなか辿り着かない。
今、デジタル化したものがあればとても便利なのは、吉川弘文館の「国史大辞典」15巻(17冊)だ。出版社が発行してくれればありがたい。しかし当面は重いものを抱えながら机に運ぶ必要がありそうだ。
大きな課題がPCの能力だ。現在使用中のPCは何とか応えてくれてはいるものの、反応速度は今ひとつ。「すぽん!」ではなく「す~う ぽん!」なのだ。もう少しレスポンスタイムが速くなるといいなと思っている。
解決策は、スキャンの解像度をさげればよいのだが、下げると今度は拡大したときのざらつきが気になる。
つまりは、PCの能力向上待ちであるが、さて我が身の人生了までに、どこまで辿り着くことだろう。
本の断捨離
2018年6月28日
初めて買ってもらった、昭和33年の国語辞書。もう60年以上前のこと。知らない言葉をマーキングして覚えた。



本の断捨離事始め
2018年6月28日
断捨離は本から。とはいうものの‥ (2018年6月19日)
もうあと1年あまりで70歳。身の回りの品々の断捨離が急速な課題として浮上してきた。
しかし家には物が集積していて途方にくれる。そこでまず本や雑誌、書類から始める事に。
歴史学者だった父の本と自分が買い求めた本がいま東京の本棚15本ほどに同居している。庭の物置には段ボール箱が山積みだ。かつて3トンほど処分したのだがちっとも減った感じがしない。知り合いは読んだ本を次々にくれるので寝床の周りも本だらけ。
本には寿命がある。本は湿気を吸い黴と虫食いでだめになる、研究書や論文はそれを基に若手研究者が新しい研究書を書くのでその使命を果たし終える。そして翻訳書は新訳が出版されて読み易くなる。そこで覚悟を決めて断捨離に着手しようと考え始めた。そこでまず手元の何冊かを手に取ってみた。
■「津軽百年食堂」(森沢明・小学館) (6月19日)
生まれ育った弘前市内の地名やら、「津軽そば」の古い思い出が以前にも増して深く心に飛び込んで来た。市井の人びとを取材し、その心を温かく描いた小説。書棚に戻す。断捨離失敗。
■「教養としてのテクノロジー」(伊藤穣一・NHK出版) (6月19日)
かつて一緒に仕事をしたK君がコーディネートして出版したもの。仮想通貨・ブロックチェーンから始めていたので、フロー系の本と思われたが、読み進むうちに、現在のデジタル社会の引き起こす変化を日本人が丁寧に考えなければ、世界から後れを取ることが分かりやすくひもとかれていて、考えさせられた。断捨離失敗。書棚に戻す。
■江戸の骨は語る」(篠田謙一・岩波書店) (6月19日)
江戸切支丹屋敷から出土した3体の遺骨をDNA分析して、そのひとつが、宣教師シドッチの物であることを確認し、復顔するまでの経緯を辿った書。氏は分子人類学の専門家で医学博士。DNA分析の下りは詳細すぎて素人には辟易気味だったが、読んでつくづく感心するのは、歴史に関心を持つ理科系の人々は、基本的な言葉のひとつひとつを丁寧に反芻しながら定義しひもといてゆくことだ。その結果、読者はすぅ~っと理解が進む。
本書を読んで連想し本棚から取り出したのは、「奇会新井白石とシドティ」(垣花秀武・講談社)である。垣花氏も物理学者である。その出だしは、「浪人」を使うか「牢人」を使うかという吟味から始まる。こうした事は文科系の書物や論文では説明がされないか、せいぜい脚注に一行乗る程度。書き手としては、そんなことは常識であり知らないのは勉強不足という事なのだろうが、素人は取り残されてしまう。次世代の人々の理解を進めるということでは重要な事と思う。2冊の断捨離失敗。書棚に戻す。
■これでは本の断捨離は進まない!! (6月26日)
読みだすと懐かしく一層の愛着が湧くので手放せなくなってしまう。
あらためて、本を大きくフロー系(実用書、ハウトゥー本、技術書、語学書、版を重ねている辞典など)とストック系(古典)の大きなふたつにわけて、まずフロー系から捨てることを算段することにしてみた。しかし… それも、そう簡単には行くものだろうか。
bottom of page