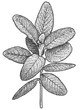家の古い引き出しから、ひとまとまりの新聞類が出てきた。
最初に眼に飛び込んで来たのは、昭和32年の尾鷲駅から九鬼駅に出発する蒸気機関車の写真。国鉄・紀勢東線が尾鷲-九鬼間で開通したのだ。
尾鷲までの鉄道は昭和9年に開通したのだが、そこから九鬼までの11キロは23年もの長い時間がかかった。その一番列車が九鬼に向けて出発した。資料をもとに、その日を振り返ってみると…

開通日の昭和32年1月12日の九鬼駅は、それはそれは大変な人込みだった。
人々がホームに溢れ、小旗を振って一番列車を迎えた。初めて列車を見る小中学生も多かった。鉄道開通の祝歌が作られた。町内に仮装行列が繰り出し、夜には提灯行列で海岸通りは人の波でぎっしり。町には映画館が二館あったが無料開放。朝日新聞三重版では、「お祭り以上のさわぎ」と見出しが踊った。九鬼駅開通は、地元には「父祖三代の悲願」(紀勢新聞、南海日日)であった。南海日日は二面に特集記事「喜びにわく鰤の九鬼」を組んで、九鬼の沿革を簡潔にしかしわかりやすくひもといている。なにしろ、この路線は過去3度に亘り工事が中断され、4度目にして実現した経緯があったからだ。






メディアの意気込みにも大変なものがあった。
朝日新聞社は航空機、毎日新聞社はヘリコプター��を飛ばして上空から一番列車を撮影した。毎日は号外を出し、その見出しは「『陸の孤島』に汽笛一声」というもの。NHKは開通当日の模様を録音し名古屋から全国放送した。
私は津軽・弘前の映画館のニュース映画で、小旗を振って列車を迎える祖母の姿を見た。ニュース映画社も来ていたのだ。難工事が続いたこともあり全国的にも注目されていた鉄道だった。
紀勢新聞より
鉄道開通により、九鬼には一日上下それぞれ七本の列車が発着。尾鷲までの時間は、わずか20分前後になった。それまでの巡航船55分、国鉄バスでの1時間半に較べ、時間的に大幅に短縮された。それだけではない。揺れが少なく快適さが全く違った。そして大阪・名古屋の経済圏へと繋がった。
紀勢新聞の1月12日付によると、巡航船を運営していた熊野商船は、鉄道開通により、尾鷲~九鬼間の運賃を、それまでの70円から40円に大幅値下げした事を伝えている。また南海日日新聞によると、この頃、九鬼の戸数は600、人口2600だったという。
(注)昭和34年 7月15日に紀勢本線賀田駅~二木島駅同時開業し、紀勢本線は全線開通
(運賃 尾鷲-大曽根浦間二等20円、三等10円という。なお尾鷲九鬼間の運賃は調査中。)
その後、鉄道工事は進み、昭和34年(1959)には紀伊半島をぐるりと回る紀勢線全線が開通した。しかし…、
尾鷲市が昭和49年(1974)に発行した「尾鷲市制20周年記念要覧」には、次のような記述がある。
「待望の紀勢本線が全通して、陸の孤島といわれていたこの地方の社会環境は一変した。しかしその後期待された観光開発をはじめ産業面ではさして発展せず、むしろ旧村部では人口の減少さえおこった。」
平成30年刊 三重県統計書によれば、
平成28年度の九鬼駅 一日当たりの利用客数は19 人である。